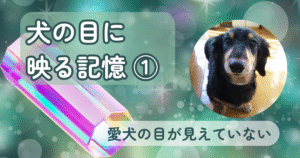2014年に旅立った愛犬(ダックスフンド)が、
進行性網膜萎縮症で2歳で失明した当時のことを振り返りながら記しています。
確定診断後、飼い主として出来ることを模索し始めた頃、
「目の見えない犬と飼い主のためのサークルに参加してくれませんか?」と連絡がありました。
同じ疾患を持つ犬が大勢いることを知り、何か自分にもできることはないかと考えるきっかけとなりました。
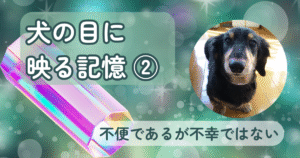
目が見えない犬と飼い主のサークル
確定診断から数ヶ月後。
「目の見えない犬と飼い主のためのサークルを立ち上げようと思うので、参加してくれませんか」と
先の動物医療センターの眼科医から連絡があった。
連絡があったときには、既に犬の目との付き合い方が落ち着いていたので、
正直、それに参加しても何かを得られるとは思わなかった。
また、自分の犬のことを、最初から話すことにも躊躇していた。
目が見えない=かわいそう、という図式に疲れていたからもある。
都度、誰かに言い訳しているようで気が進まなかった。
様々なケースがあることを知る
数ヶ月振りに医療センターを訪れると、先の眼科医の他に、
動物の行動学の教員と犬のトレーニングインストラクターが来ており、
動物看護学科の学生も多数参加していた。
集まった犬たちは、大型犬も小型犬も、犬種も様々。15頭くらい居た記憶がある。
こんなに多くの目の見えない犬たちが居るんだな、と改めて感じた。
私の犬の様に、進行性でゆっくり見えなくなっていったケースや、突発性で24時間以内に失明したケース。
階段やソファを難なく昇降できる犬や、一方、見えなくなったことにより出来なくなってしまった犬。
自己紹介がてら、犬の現在の様子を説明した。
飼い主さんの表情も様々で、戸惑いを隠せない方が居る一方、
私のように、すっかりその状況に慣れてしまっているケースもあるなど、実に様々だった。
犬の目の見える仕組みを学ぶ
大学病院の動物医療センターゆえ、そのサークルには動物看護師を目指す学生も多く参加しており、
実際の教室で犬同伴で講義が始まった。
眼科医からは「人間と犬との視覚に頼る割合や見える範囲」や「視認性」など、興味深い話が続き、引き込まれた。
例えば、人間が視覚に頼るのは90%以上だが、犬たちは視力が0.3くらいで視覚に頼るのが30%くらい。
一方、犬たちは早く動くモノはよく見える。確かに窓の外を通るモノへの反応は早いと感じていた。
そして、目の見える波長の範囲は黄緑から青と狭いことや、犬にとって赤と緑は同じ色に見えること。
だから、犬とボール遊びをするときは、緑の芝生で目立ちやすい青いボールを選ぶと良いということ。
・・・など等、なるほど!と思う話が続く。
ふと、思ったのだが、私自身が、目の見えない犬と暮らすことに慣れてきていたからか、
私の犬も、同じく終始リラックスしていて、講義の間もずっと隣で寝ていた。
講義は興味深かったのだが、途中から、犬自身が飽きてしまい、
「帰りたい」というサインを私に出し始め、手をちょいちょい叩いて催促し始めて、
なだめるのが大変だったことを覚えている。
看護学生さんたちの提案
視覚を補助するために、学生さんたちの提案で手作りした
「犬に触覚のついた帽子(またはカチューシャ)」の試作品を試した。
特に、目が前に出ているタイプの犬種は、
壁にぶつかる前に、その触覚が前方の障害物に触れることで、危険を回避できるので好評だったようだ。
私の犬は、この段階では不自由なく過ごしていたのと、被り物自体が苦手でだったので、
せっかく学生さんが作ってくれた触覚付き帽子を断固拒否して被ってくれず、なんだか申し訳なかった。
眼科医と話してみて
帰り際、声をかけてくれた眼科医と話した。
「すみません、せっかく声をかけてくださったのですが、
私も犬も、この目が見えない状況を普通に受け入れてしまって暮らしているので、
このサークルに参加してもご迷惑をおかけするようで・・・」
そう謝った私に、眼科医が言った。「だからお声をおかけしたんです。」
「えっ」驚いて立ち止まった私に更に告げた。
「多くの飼い主は、飼っている犬の目が見えなくなったことに悲観的になり、
その状況を受け入れられずに前に進めないでいます。」
そういえば思い出した。最初の電話で聞かれたことを。
「その後、何か困っていることがありますか?」
「特にないです。楽しく暮らしています」と答えていたことを。
状況を受け入れて楽しく暮らす
「あなたの様に、犬の目が見えないって状態を犬の個性と受け止めて、
これからも楽しく暮らすことができるということを、
眼科医が幾ら説明しても、飼い主さんには理解してもらえない。
だから、皆に、その様子を見てもらうために声をかけました。」
・・・そうか、それでいいんだ。
改めて、そう言われて、嬉しかったことを覚えている。
その大学の学園祭で、飼い主側からの視点で、と依頼され
「目の見えない犬と暮らす工夫」というテーマでトークをしたこともいい思い出だ。
当の犬は隣でいい子に・・・我関せずで、お昼寝してたけど。
ボールを追っかけての遊びは実際には出来なくなったけれど、
代わりに、音の出るオモチャを鳴らしながら遊んでいた様子を、今も鮮明に思い出すことができる。
犬自身も状況を受け入れて、本当に楽しそうだった。
ただ、覗き込んだ私の顔をこの犬はもう一生見ることはできないんだ、という、
なんとも言えない寂しさが、事あるごとに私を襲ったが、この気持ちには、なかなか慣れなかった。
飼い主としての想いや取り組んだことを当時を振り返りながら記しています。
次回は、犬を連れてお出かけした話などを記そうと思います。お付き合いいただければ幸いです。